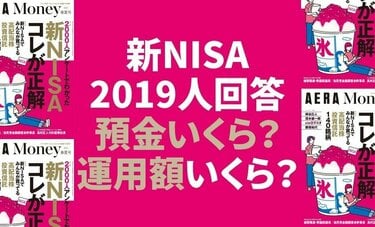外国為替市場では円安・ドル高が続いている。円安は輸入品の値上がりを通じて国内の物価をかさ上げし、家計の負担増を招く。一方で、自動車や電機、機械といった輸出関連など海外の稼ぎが多い企業には追い風だ。ドル建ての収益や資産が円安によって膨らむためだ。株式市場では円安の恩恵を受ける銘柄はすでに買われてきたが、それでもなお伸びしろがありそうな「出遅れ株」を専門家に教えてもらった。
【表】円安メリットがあるのに「出遅れている銘柄12」はこちら!
ドル・円市場は4月24日に心理的な節目である1ドル=155円を突破した。同155円台をつけるのは1990年以来、約34年ぶりだ。25日時点でも155円台前半の円安・ドル高水準で推移している。
日米の金利差が意識されていることが大きい。米国経済の好調を示す経済指標の発表が相次ぎ、当初は年3回とみられていた米国の早期利下げへの観測が後退。一方で日本でも3月にマイナス金利が解除されたとはいえ、金融緩和の状態は当面続くとみられており、両国の金利差が縮まるとの見方は薄まっている。
政府・日銀の為替介入に対する警戒感が意識されているものの、円安の流れになかなか歯止めがかからずにいる。
家計の負担をやわらげる
円安が長引けば、家計の負担もそれだけ重くなる。しかし、円安でメリットのある企業にとってはポジティブだ。米国向けなど海外の売上高比率が高い企業や、海外資産を多く持つ企業は円安になった分だけ海外での稼ぎや資産が押し上げられる。
このため、こうした円安の恩恵を受ける企業の株を買っておけば、物価高が痛手となる家計の負担をやわらげる助けになるかもしれない。
 池田正史
池田正史